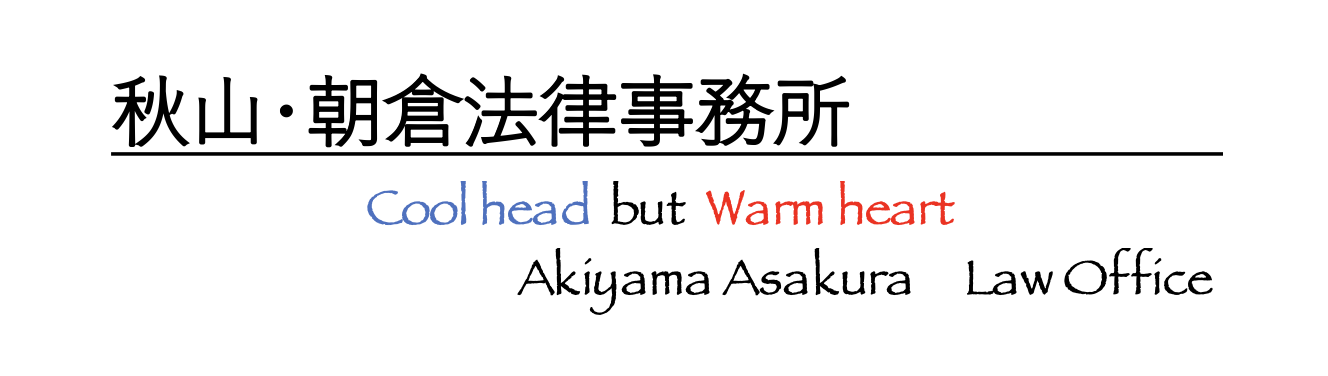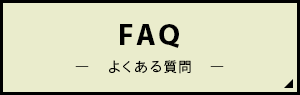少額訴訟制度の利用法
1 少額訴訟制度の概要
(1) 近時、裁判の簡易・迅速化の要請がさけばれております。
このような要請は、裁判を提起して時間をかけてまで回収すると、費用倒れになってしまうような請求額が比較的少額な事件においては、特にあてはまると思います。
また、弁護士に依頼することなく、当事者本人でも訴訟を提起できるよう手続きの簡易さが必要な場合もあると思われます。
そこで、今回は、裁判手続きの一種として、裁判の慎重さよりも簡易迅速さを重視し、また、当事者本人でも裁判を行えるよう簡易裁判所が種々の工夫をしている少額訴訟制度をご説明したいと思います。
(2) 少額訴訟は、原則として1回の期日で審理を終え、直ちに判決の言渡しがなされるという簡易・迅速な裁判手続きの一種です。
従って、逆に、争点が多い事件、立証が難しい事件、複雑な事件を審理するのに少額訴訟は向いておりません。
少額訴訟に適した事件としては、契約書等の証拠書類が揃っている貸金返還請求訴訟、滞納家賃の支払請求訴訟、敷金返還請求訴訟等であるといえます。
2 少額訴訟制度の手続・要件
(1) 少額訴訟における請求金額は金60万円以下でなければなりません。
平成16年4月1日からこれまでの請求金額30万円以下という要件が上記60万円以下という要件に引き上げられました。
なお、ここにいう請求額とは遅延損害金を含まない元本金額を言います。
(2) 当事者は、原則として、第1回の期日までにすべての主張や証拠を裁判所に提出しなければなりません。また、証拠調べは、期日にすぐに取り調べることのできる証拠に限ってすることができます。
従って、当事者は、裁判期日までにきちんと契約書や領収書などの証 拠書類や証人などの準備を整えていなければなりません。
(3) 被告が少額訴訟での裁判に同意しない場合には、通常訴訟に移行します。
また、被告が判決に異議を申立てたときも通常訴訟に移行します。
前記のように、この訴訟は原則1回の裁判で審理を終えますから、きちんとした反論をしたいが準備が整わないといった被告の立場では、第1回の裁判期日で通常訴訟への移行を主張するべきでしょう。
(4) 裁判所は、被告の支払能力・資力等を考慮して、一括払いではなく分割払いの支払を命ずる判決を言い渡すことができます。原告は、この分割払いの判決に対する異議は申立てられません。
(5) 少額訴訟の訴訟費用は、訴状に貼る若干の印紙代(請求額30万円の訴訟でも3,000円)と若干の郵便金手代がかかるのみです。
従って、訴訟の提起自体は、低額の費用ですることが可能です。
3少額訴訟に必要な準備
(1) 少額訴訟といっても、訴状の提出や証拠書類の収集・提出は、当事者本人の責任で行う必要があります。その意味では通常の訴訟とは異なるものではありません。
それも、原則1回の審理で終る裁判期日までに全ての証拠書類を整理して提出しなければなりませんので、周到な準備が必要なことは言うまでもありません。
(2) 例えば、賃貸人が賃借人に対し滞納家賃30万円の支払を求めて訴訟を提起する場合には、①賃料が月額何円であったか、②賃料の支払日は毎月いつになっていたか、③賃借人は何月分から何月分までの家賃を滞納しているのかを訴状において特定して主張しなければなりません。
また、①②の主張を立証するために賃貸借契約書が必要です。
これに対し、③の家賃滞納の事実については、むしろ賃借人の方が賃料を弁済したという事実を領収書等によって立証する責任がありますので、賃貸人側が賃借人の滞納の事実を積極的に証明する必要はありません。
(3) また、賃借人からの敷金返還請求訴訟では、原状回復費用の敷金からの控除をめぐって紛争になるケースが多くあります。
このような原状回復費用の控除の主張については、賃貸人側が主張・立証する責任があります。
従って、賃貸人は、まず、原状回復工事・費用の明細書、領収書等を提出するなどして、原状回復費用の金額を立証しなければなりません。
また、住居用の賃貸アパートの場合には、たとえ賃貸借契約書に「原状回復費用を賃借人の負担とする」旨の条項があったとしても、原状回復費用を賃借人に負担させることができるのは「賃借人の故意・過失による毀損」の場合でなければなりません。
部屋の損耗・毀損状況が通常の使用により生ずるような自然損耗による場合には、いままでに支払われてきた賃料の中で賃貸人側が負担すべきものとされます(詳しくは、本稿第2回及び第18回の原稿を参照して下さい)。
そこで、部屋の毀損状況が通常の使用によるものではなく、「賃借人側の故意・過失」によることを立証するために、退去時の部屋の状況を写した写真を提出するなどして立証する必要があります。
(4) 次に、訴状の書き方ですが、貸金返還請求訴訟や滞納家賃の支払請求訴訟などの場合には、訴状の定型書式が簡易裁判所に置いてありますので、これを利用すると良いでしょう。
また、訴状の書き方や提出が必要な証拠書類などについても、簡易裁判所の書記官が指導してくれますので、事前に簡易裁判所に赴き相談すると良いでしょう。
もっとも、裁判所書記官は、公正な第三者的な立場での指導にとどまりますので、訴訟に勝つための方策の相談については、弁護士に相談されるのがいいでしょう。