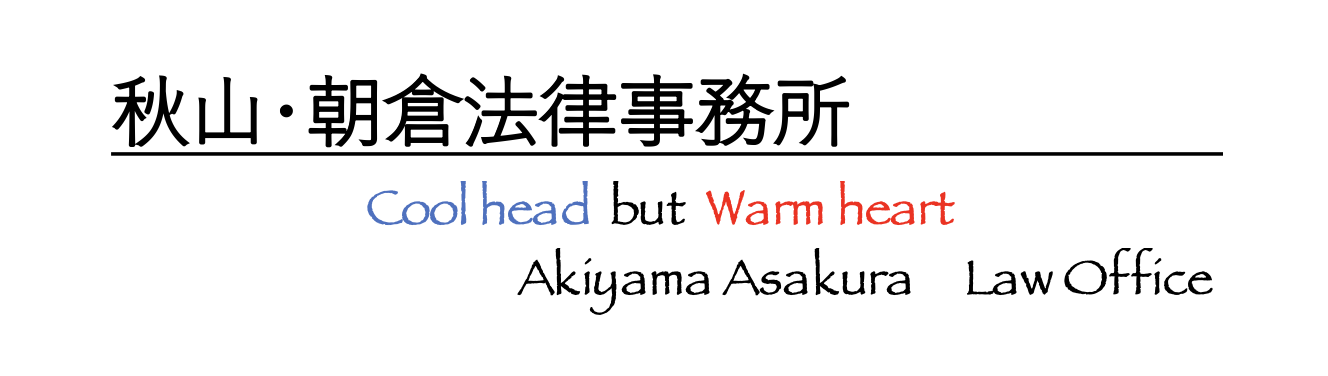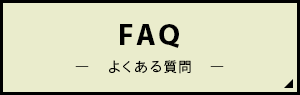抵当権者による賃料債権に対する物上代位
第1 問題の所在
抵当権は抵当目的物の交換価値(担保価値)を把握する権利ですから、何らかの理由により目的物の交換価値が現実化した場合、この価値代替物にも効力を及ぼすのが妥当です。このように、抵当権者が、目的物の滅失・毀損等によって債務者が受けるべき金銭その他の物から優先弁済を受けることを物上代位といいます(民法372条、304条)。
ところで、近時の不動産不況下においては、抵当不動産の競売によるよりも、抵当権設定者が抵当不動産を第三者に賃貸している場合の賃料債権に対して物上代位権を行使することによって債権の回収を図る方が簡便であることから、抵当権者が賃料債権に対して物上代位権を行使する例が増加しています。
しかし、賃料は、抵当不動産の法定果実であって、目的物の滅失・毀損によって債務者が受ける金銭等の価値代替物とは性質が異なり、物上代位の対象になるのかどうか問題とされてきました。
第2 賃料に対する物上代位
1.学説
この点、学説上は、物上代位権の法的性質をどう考えるかと関連して、賃料に対する物上代位を肯定する見解と否定する見解とが争われてきました。
肯定説は、抵当権の効力は交換価値の現実化した物にも当然に及ぶとの理解に立って、不動産の交換価値の「なし崩し的現実化」である賃料にも及ぶべきであると主張しました。304条が、賃料についても規定しているし、実質的にも、抵当不動産を競売するより、賃料から債権の満足を得る方が関係者の利益にも合致するというのです。
他方、否定説は、物上代位権は抵当権者保護のために認められた特権であり、あまり拡張的に認めるべきではないという理解に立って、目的物使用の対価である賃料に対する物上代位を認めると、抵当権設定者の使用収益権(賃貸権限)を害するので、認めるべきでないと主張しました。
2.判例
このような状況下で、最高裁判所は、平成元年10月27日に、賃料債権に対する抵当権の物上代位を認めても抵当権設定者の使用収益権を害さないと述べて、これを全面的に肯定する判決を下したのです。
第3 その後の動向
1 この判例が出てから、先に述べたように不動産価格の低落に伴い、抵当権者が賃料債権に対して物上代位権を行使する事例が急増することになりました。
しかし、他方で、抵当権設定者側の自衛手段として、物上代位を妨害するような行為も多発することになったのです。
2.賃料債権の譲渡
抵当不動産の所有者(賃貸人)が抵当権者による賃料債権の差押前に賃料債権を第三者に包括的に譲渡してしまうということがあります。抵当権者が物上代位権を行使するためには被代位債権をその「払渡し又は引渡し前に」差し押さえる必要があります。
この場合、賃料債権の譲渡が「払渡し又は引渡し」に該当するかどうかが問題となります(該当すれば、それに遅れた物上代位は認められないことになります)。
この点、学説上は見解が対立していましたが、最高裁判所は、平成10年1月30日、債権譲渡は「払戻し又は引渡し」には該当せず、抵当権者は、賃料債権が譲渡されても、賃借人が賃料を譲受人に支払ってしまわない限り、これに対して物上代位権を行使できるという判決を下しました。
3.賃料債権と賃借人の債権との相殺
次に、抵当不動産の賃借人が、抵当権の物上代位により差し押さえられた賃料債権と自己の賃貸人に対して有する一般債権とを相殺してしまうという事例が問題となりました。
物上代位による債権回収の利益と相殺による期待利益のいずれを優先させるべきかは困難な問題であり、下級審の判断も分かれていました。
この点、平成13年3月13日の最高裁判決は、物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されているから、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差押えた後は、賃借人は抵当権設定登記後に賃貸人に対して取得した債権と賃料債権との相殺をもって抵当権者に対抗できないとして、物上代位を優先させる判決を下しました。
4.転貸賃料債権に対する物上代位の可否
このように判例を見てくると、抵当権者による物上代位の範囲がかなり拡大される傾向にあるように思えます。しかし、次の判例では、物上代位の拡大傾向にやや絞りがかけられているようにも見受けられます。
最高裁決定平成12年4月14日の事案は、抵当権設定者が抵当不動産を賃貸し、賃借人が更にそれを転借人に転貸したところ、抵当権者が賃借人(転貸人)の転貸賃料債権に対して物上代位権を行使したというものです。
転貸賃料債権に対する物上代位の可否については下級審・学説上争われてきましたが、最高裁は、抵当不動産の賃借人(転貸人)はその不動産について物的責任を負う者ではないから自己の賃料債権を抵当権者に供すべきいわれはなく、転貸賃料債権を物上代位の対象とすると賃借人の利益を害するという理由で、抵当権者の転貸賃料債権に対する物上代位を認めませんでした。
このように、判例は、物上代位にも限界があることを認めて賃借人を保護したのですが、もちろん、物上代位を回避するために転貸借を仮装して、賃料債権に対する物上代位の実効性を失わせるという事態までが許される訳ではありません。上記最高裁決定も、「抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合」には物上代位権を行使する余地を残すという安全弁を付けている点には注意が必要です。