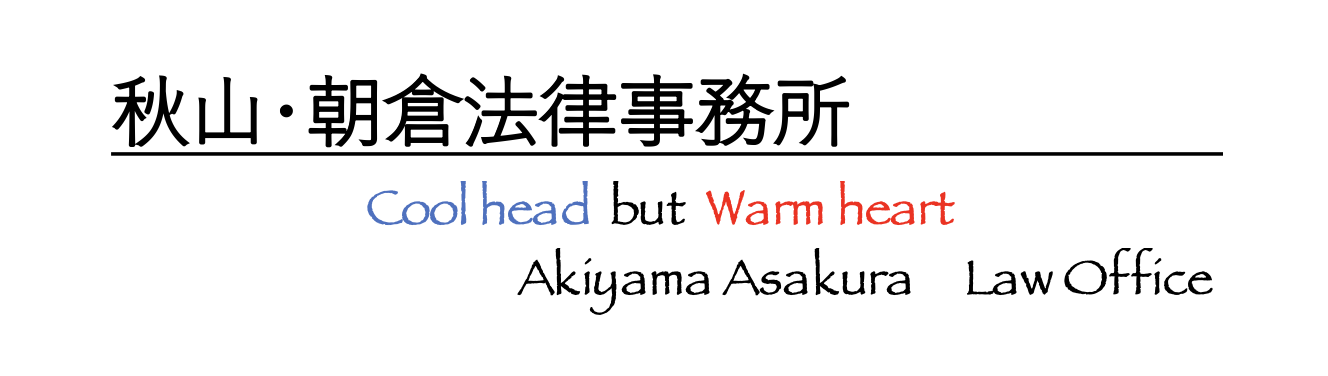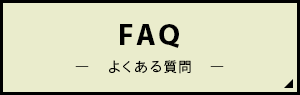管理監督者と残業代請求
<質問>
当社では、2つの店舗で不動産仲介業を行っております。近時、あるファーストフードチェーン店の店長が労働基準法上の管理監督者ではないとして残業代を請求した事案で、裁判所は会社に対し残業代の支払いを命じたと聞きました。
当社の場合でも2つの店舗の各店長には残業代を支払わなければならないのでしょうか。
<回答>
1 労働基準法41条2号では、「監督若しくは管理の地位にある者」に関しては、労基法の労働時間、休憩、休日の規定が適用されず、残業代の支払義務がないとされております。
この「管理監督者」とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者」を指すものと解されており、一般の大企業で言うならば、部長、課長クラス、工場長クラスがこれに当たりますが、形式的な役職の名称に関わらず、「管理監督者」に該当するか否かは労働実態に即して具体的に判断されます。
2 そして、その具体的な判断基準は、①職務内容や職務遂行上、使用者と一体的な地位にあるといえるほどの権限を有し、これに伴う責任を負担していること、②出退勤について裁量があり、時間拘束が弱いこと(例えば、タイムカードで出退勤を管理され、遅刻や欠勤に対し賃金控除されるような労働者はこれに該当しない)、③基本給、役付手当、ボーナスの額において、一般の労働者に比べ優遇され、その責任と権限にふさわしい待遇を受けていること、という各要件を満たしているかを総合考慮して判断されます。
そして、店長、営業所長という肩書が付いている場合であっても、上記のような各要件を満たしている者は一部の者に限られるのが一般的でしょう。
前記のファーストフード店の店長の事案で東京地判平成20年1月28日(判時1998-149)は、「ファーストフード店の店長の職務と権限は店舗限りのもので、経営者と一体となって本法の労働時間規制の枠を超えて事業活動することが必要なものではなく、また、管理監督者としての待遇がなされていたわけでもない」として、管理監督者該当性を否定しております。上記の事案は、全国に多数の店舗を持つファーストフードチェーン店の場合には、店長と言ってもその地位や権限は、当該店舗内に限られ、本社の正社員(平社員)よりも高いとは言えないという実情に照らし、上記②の要件は満たしていても、上記①③の要件について否定的に解した為、管理監督者の該当性を否定した事案と言えます。
3 本件については、前記のようなファーストフードチェーン店とは異なり、わずか2店舗しかない店舗の店長ですので、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体となって従業員を管理する必要性は必ずしも否定されるものではありません。
したがって、前記①~③の各要件を満たせば、管理監督者として認められる可能性は十分にあるでしょう。