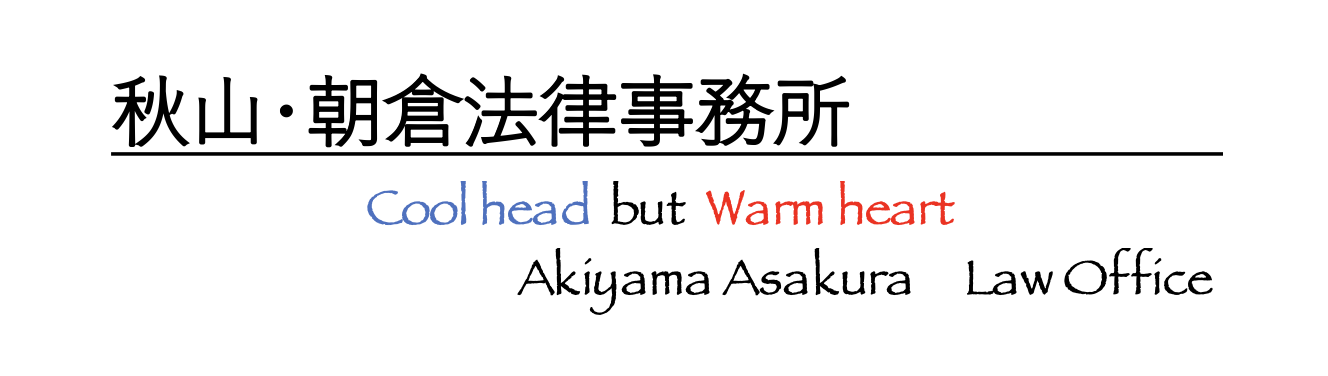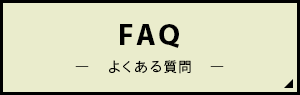賃借物件の所有者が変更した場合の賃借人の権利
(質問)私が借りている賃借物件が売却され所有者が変わってしまいました。私は、このままこの物件に住めるのでしょうか。また、敷金は誰に請求したらいいのでしょうか。
(答え)
1 売買による所有者の変更の場合
売買により所有者が変更する場合にも、賃借権を新所有者へ対抗できる場合には、賃借人はその建物にそのまま住み続けることができます。
賃借権を新所有者へ対抗できる場合とは、賃借権の登記をしている場合だけでなく、建物の賃貸借契約の場合には、現に建物に居住していることも含みますので、通常の場合は新所有者に対抗できます。建物所有目的で土地を借りている場合にも、判例上、借地上の建物を自分名義で登記していれば、新所有者に対抗できるとしています。
このような場合、敷金返還義務も当然に新所有者に引き継がれるので、新所有者にも請求できます。
但し、旧所有者のもとで家賃を滞納していた場合には、滞納家賃が敷金と精算(相殺)されてしまうので、敷金から滞納家賃分を差し引いた残額のみ新所有者に引き継がれます。また、敷金額が家賃と比して著しく高額な場合は、その名目如何にかかわらず賃貸借契約時に差入れた金銭は「敷金」ではなく「保証金」と見なされるので、この場合も新所有者には引き継がれません。
2 競売による所有者の変更の場合 競売により所有者が変更した場合には、たとえ建物を借りて居住していたり、借地上の建物の登記をしていても、賃貸借契約の締結前に、抵当権の設定登記がなされており、その抵当権の実行によって競売された場合には、賃借人は、新しい所有者に賃借権を対抗することはできません。したがって、敷金の引き継ぎもありません。
競売による所有権の変更が為された場合、賃料を新しい所有者に支払うことで、6ヶ月間は当該建物に住み続けることができますが、新しい所有者と新たに賃貸借契約を結ばない限り、6ヶ月後に退去しなければなりません。